第3回ミューズキャット
☆楽器博物館の見学(武蔵野音楽大学)☆
武蔵野音楽大学の構内にある博物館には、鍵盤楽器、ヴァイオリン、ハープ、チェロ、アジア、アフリカ、各地の民族楽器の展示室があり、1時間30分程の解説を受けながら、普段目にすることができないめずらしい、貴重な楽器を見学することができました。
***展示楽器***
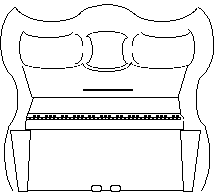 ナポレオンの帽子型ピアノ(1853年6月フランス皇帝ナポレオンIII世の結婚祝いの品としてイギリスのヴィクトリア女王が贈呈しました。ピアノそのものがナポレオンの帽子をかたどってあり、ペダル部分にまで彫刻がなされています)
ナポレオンの帽子型ピアノ(1853年6月フランス皇帝ナポレオンIII世の結婚祝いの品としてイギリスのヴィクトリア女王が贈呈しました。ピアノそのものがナポレオンの帽子をかたどってあり、ペダル部分にまで彫刻がなされています)
- ヴァージナル(装飾が美しい小型チェンバロ)
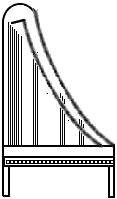 ハープピアノ(ハープを組み合わせたピアノでハープの音色)
ハープピアノ(ハープを組み合わせたピアノでハープの音色)
- 変形鍵盤(ドイツのヤンコが合理的な鍵盤として発明したもの)
- 移調装置付スクエアピアノ(モーツアルトが使用したといわれるピアノ)
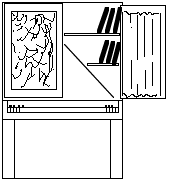 収納庫付きアップライトピアノ(まだ弦を斜めに張ることがされていないため左右対称に作っていなく見た目だけ左右対称にするために箱に入れたため隙間ができたのでそこに棚を作ったものです)
収納庫付きアップライトピアノ(まだ弦を斜めに張ることがされていないため左右対称に作っていなく見た目だけ左右対称にするために箱に入れたため隙間ができたのでそこに棚を作ったものです)
- ジュークボックス式オルゴール(1ペニーを入れると選曲したオルゴールを聞くことができます)
- 円盤式オルゴール
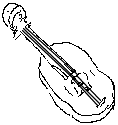 ヴィオラ・ダモーレ(ヴィオール式バイオリン、目隠しした天使の顔の彫刻が施されています)
ヴィオラ・ダモーレ(ヴィオール式バイオリン、目隠しした天使の顔の彫刻が施されています)
- アイリッシュハープ
- シュランメル・ギター
- ラケット
- クルムホルン
- トロンバマリナロシュキ(スプーン型楽器)
- ハーディガーディ
- タウス(孔雀型の北インドの弦楽器)
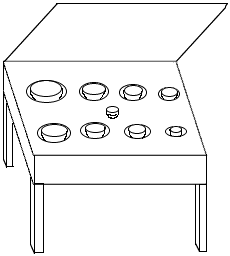 グラスハーモニカ(グラスの縁を濡らした指先で擦するとなんとも不思議な響きです)
グラスハーモニカ(グラスの縁を濡らした指先で擦するとなんとも不思議な響きです)
- 馬、羊の頭の彫刻のあるモンゴル系の琴
- 筑紫甞
- そのほか馬の頭蓋骨や人間の頭蓋骨を使ったという不気味な楽器("お払い"は3回してあるそうです)など・・・。
グラスハーモニカ以外は、手に取って演奏は出来ませんが、博物館の方による演奏で実際にその時代と情景を思わせる音色を聞くことができました。
どれも、美術的にもすばらしく、歴史と文化の流れを感じさせるものばかりで、1時間30分のタイムマシーン世界一周音楽の旅はあっという間に終わりました。
***解説から***
●ヴィオールとヴァイオリンの発生については諸説あるようで、文献によって書いてあることが違ったりするのですが、最近有力な説として次のように解説してもらいました。
- ヴィウエラが変化してヴィオールになった。
- ヴィオールとヴァイオリンは全く別の楽器として発達した。
- ヴィオールは7コース14弦もあり、調律がやっかいであった。
また、ヴィオールは調が固定されてしまい、転調のある曲などは演奏しにくかったことから、4弦の調律で済み、5度調律すると転調も容易なヴァイオリン属がよく使われるようになったそうです。
●ピアノは時代を追って様々に工夫が施されて現在のような形になったのですが、対照的にヴァイオリンは、最初から完成された形になっていました。
いろいろ工夫を試みる人もあったのですが、結局定着しませんでした。
●ン千万円の名器もたくさん、一見無造作に展示されていました。優秀な学生に貸与することもあるとのことで、その日もコントラバスが1台、演奏会用に出張中でした。
●ハーディーガーディーはパリの蚤の市でみつけたものだそうです。
ううむ、今度ヨーロッパに行ったら何か探してみよう。
実は今まで、机に置いて演奏するものだと思っていたのですが、肩紐がついていて、道端で立って演奏できるものだったんですね。
●わざわざビリビリという雑音(振動音)が出るようにしています。
こういった雑音は、ヨーロッパの現代楽器には珍しいですが、世界の民族楽器には普遍的に取り入れられているものだそうです。
そういえば、前回聴いたフィドルの演奏法でも、メロディーのほかに隣の弦を使ってアクセントのように振動音を入れていました。
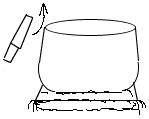 ●日本の楽器ということで木魚や鐘もありました。以前僧侶が見学に来たときに、鐘の叩き方を指導してくれた、とか。
ばちを下から上に向かって45度の角度で叩くのがこつなんだそうです。
●日本の楽器ということで木魚や鐘もありました。以前僧侶が見学に来たときに、鐘の叩き方を指導してくれた、とか。
ばちを下から上に向かって45度の角度で叩くのがこつなんだそうです。
武蔵野音楽大学楽器博物館
所在地 武蔵野音楽大学江古田校地
東京都練馬区羽沢1-13-1
TEL 03-3992-1121
西武池袋線江古田駅下車徒歩5分
ミューズキャットの案内に戻る
あむりすホームページに戻る
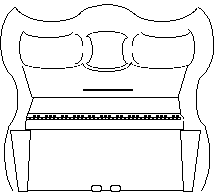 ナポレオンの帽子型ピアノ(1853年6月フランス皇帝ナポレオンIII世の結婚祝いの品としてイギリスのヴィクトリア女王が贈呈しました。ピアノそのものがナポレオンの帽子をかたどってあり、ペダル部分にまで彫刻がなされています)
ナポレオンの帽子型ピアノ(1853年6月フランス皇帝ナポレオンIII世の結婚祝いの品としてイギリスのヴィクトリア女王が贈呈しました。ピアノそのものがナポレオンの帽子をかたどってあり、ペダル部分にまで彫刻がなされています)
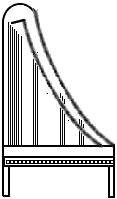 ハープピアノ(ハープを組み合わせたピアノでハープの音色)
ハープピアノ(ハープを組み合わせたピアノでハープの音色)
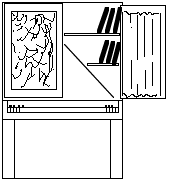 収納庫付きアップライトピアノ(まだ弦を斜めに張ることがされていないため左右対称に作っていなく見た目だけ左右対称にするために箱に入れたため隙間ができたのでそこに棚を作ったものです)
収納庫付きアップライトピアノ(まだ弦を斜めに張ることがされていないため左右対称に作っていなく見た目だけ左右対称にするために箱に入れたため隙間ができたのでそこに棚を作ったものです)
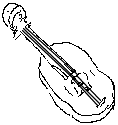 ヴィオラ・ダモーレ(ヴィオール式バイオリン、目隠しした天使の顔の彫刻が施されています)
ヴィオラ・ダモーレ(ヴィオール式バイオリン、目隠しした天使の顔の彫刻が施されています)
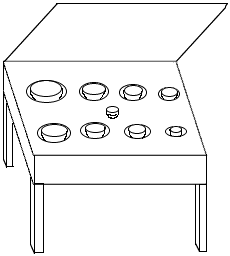 グラスハーモニカ(グラスの縁を濡らした指先で擦するとなんとも不思議な響きです)
グラスハーモニカ(グラスの縁を濡らした指先で擦するとなんとも不思議な響きです)
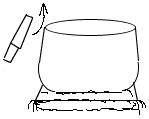 ●日本の楽器ということで木魚や鐘もありました。以前僧侶が見学に来たときに、鐘の叩き方を指導してくれた、とか。
ばちを下から上に向かって45度の角度で叩くのがこつなんだそうです。
●日本の楽器ということで木魚や鐘もありました。以前僧侶が見学に来たときに、鐘の叩き方を指導してくれた、とか。
ばちを下から上に向かって45度の角度で叩くのがこつなんだそうです。